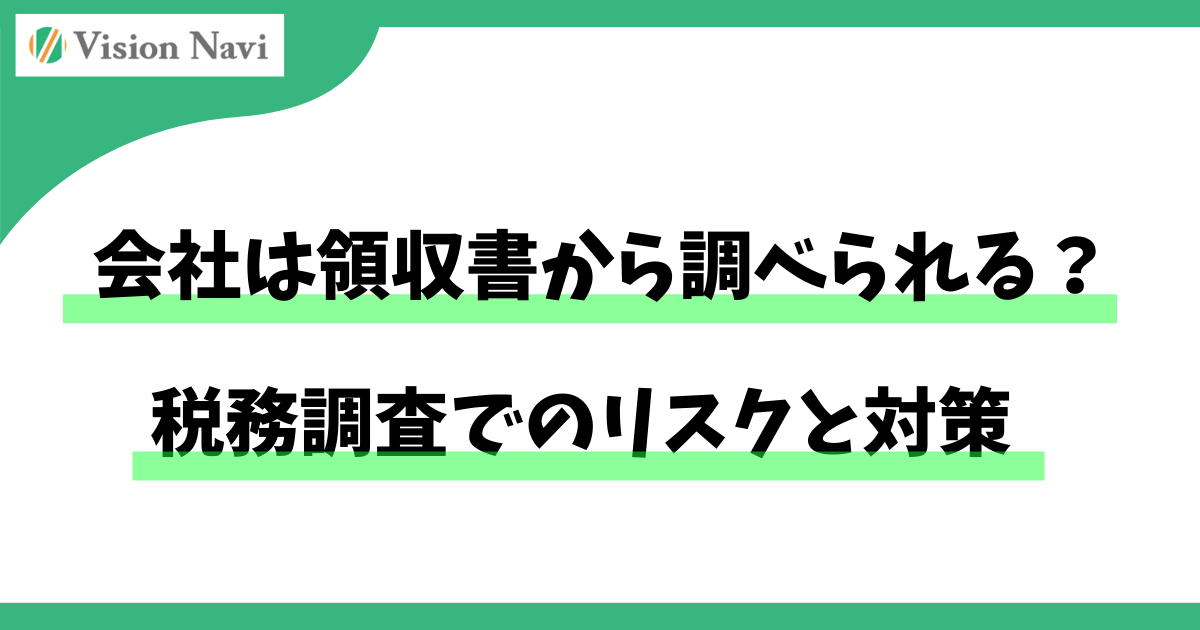こんにちは、税理士法人ビジョン・ナビです!
「税務調査で領収書を全部見られるのでは?」と不安に思う経営者の方は多いのではないでしょうか。日々の経費精算で集めた領収書は、税務署にとって会社の取引やお金の流れを確認する重要な証拠資料です。
この記事では、税務署が領収書から何を調べるのか、領収書管理の不備で起こり得るリスク、そして実践すべき対策 を分かりやすく解説します。読めば、税務調査への不安を減らし、安心して経営に集中できるはずです。
税務署は領収書から何を調べるのか?
経費の正当性
税務署がまず確認するのは「経費が本当に事業に必要だったのか」という点です。例えば、
-
接待交際費:誰と、どんな目的で使ったのか
-
交通費:業務に関係ある移動かどうか
-
消耗品費:私的利用ではないか
といった内容を領収書や説明で裏付けられるかどうかを見ています。
架空経費や二重計上の有無
同じ領収書を複数回計上していないか、実際には発生していない取引を経費にしていないか、といった点もチェックされます。
売上との整合性
経費だけでなく、売上とのバランスも見られます。
「売上規模に対して経費が不自然に多い」「経費内容が業務内容と合わない」場合、領収書をさらに詳しく調べられることがあります。
領収書管理の不備で起こるリスク
税務調査で否認される可能性
領収書に 宛名や用途が記載されていない 場合、税務調査では「事業に関係のない支出」と判断されることがあります。
その結果、経費として認められず、法人税や所得税の 追加納付 を求められる可能性があります。
役員賞与とみなされた場合のリスク
特に法人の場合、事業と無関係と判断されると 役員賞与 とみなされ、次のような負担が発生する可能性があります。
- 経費が否認されることによる 法人税の追徴
- 役員賞与として扱われることによる 源泉所得税の追徴
- 経費否認に伴う 消費税の追徴
まさに「トリプルパンチ」の状態になってしまうのです。
重加算税・延滞税のリスク
経費の不正計上が悪質と判断されれば、重加算税(最大35〜40%)や延滞税 が課される可能性もあります。特に故意の隠蔽や仮装がある場合は厳しく追及されます。
金融機関からの信用低下
税務調査で経理処理のずさんさが発覚すると、金融機関の融資審査にも影響する可能性があります。会社の信用力を守るためにも、領収書の適正管理は欠かせません。
領収書管理で実践すべき対策
1. 領収書には用途や相手先を記入する
「誰と・何のために」使ったのかを簡単にメモしておくと、税務署から質問されたときにスムーズに説明できます。
2. 電子保存を活用する
2022年から電子帳簿保存法が改正され、スキャナ保存や電子データでの保管も認められるようになりました。検索性が高まり、紛失リスクも減少します。→ 国税庁|電子帳簿保存法
3. 経費精算ルールを社内で統一する
領収書の提出期限、記載内容、承認フローなどをルール化しておくことで、税務調査での説明が容易になり、トラブルを防げます。
4. 税理士に定期的にチェックしてもらう
日々の仕訳や領収書の扱いに不安がある場合は、税理士に定期的にチェックしてもらうのがおすすめです。
ポイント整理
-
税務署は領収書から「経費の正当性・架空経費の有無・売上との整合性」を調べる
-
宛名・用途が不明な領収書は経費否認のリスクがある
-
不正や管理不備があれば、追加課税・重加算税の可能性も
-
対策は「用途記録・電子保存・社内ルール化・専門家チェック」
よくある質問Q&A
Q1:領収書を紛失した場合はどうすればいいですか?
A1:支払先から再発行してもらうのが基本です。再発行が難しい場合は、出金伝票を作成し、日付・金額・用途を明記することで代替できます。ただし、多発すると税務署の疑念を招きますので注意が必要です。
Q2:クレジットカード明細だけでも経費として認められますか?
A2:原則として領収書が必要です。ただし、インターネット取引などで領収書が発行されない場合は、利用明細や請求書と合わせて保存することで認められるケースもあります。
まとめ
会社の領収書は、税務署が経費の妥当性を確認するための重要な資料です。管理が甘いと経費否認や追加課税、信用低下といったリスクにつながります。
だからこそ、日々の管理を徹底し、電子保存や社内ルール化で仕組みとして整えること が大切です。そして、万が一税務調査が入っても慌てないよう、専門家のチェックを受けておくのが安心です。
税理士法人ビジョン・ナビでは、領収書管理から税務調査対策まで幅広くサポートしています。無料相談も承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください!