こんにちは、税理士法人ビジョン・ナビです!
「うちは相続税なんて関係ないと思っていたけど、念のために聞いておきたくて…」
そんなご相談をいただくことが増えています。
相続税は、一定以上の財産があると発生する税金ですが、ちょっとした対策の有無で数百万円の差が出ることも。
しかも、相続税は亡くなったあとでは対策がほぼできないため、生前の準備がとても重要です。
この記事では、「相続税がかからないようにするための合法的な節税対策」について、わかりやすく解説します。
“家族に迷惑をかけない”“財産を守る”ために、ぜひ早めの対策を始めましょう。
相続税がかかるかどうかの判断基準とは?
まず前提として、すべての人に相続税がかかるわけではありません。
相続税には「基礎控除額」があり、それを超えた財産に対してのみ課税されます。
基礎控除額の計算式:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば、相続人が配偶者と子2人なら、
→ 3,000万円+600万円×3人=4,800万円までは非課税です。
つまり、財産が基礎控除内に収まっていれば、相続税はかかりません。
まずは、自分の財産総額をざっくりと確認することから始めましょう。
相続税をかからなくするための主な方法
1. 生前贈与で財産を減らしておく
毎年110万円までの贈与は、贈与税がかかりません(暦年課税制度)。
この制度を活用して、数年かけて子や孫に贈与を行うことで、相続財産を着実に減らすことが可能です。
【ポイント】
-
毎年コツコツ行うのが効果的
-
贈与契約書を作成して証拠を残す
-
110万円を超えると贈与税の対象に
2. 生命保険を活用する
生命保険の**死亡保険金には「非課税枠」**があります。
→ 500万円 × 法定相続人の数
たとえば、相続人が3人なら1,500万円まで非課税に。
現金で相続されるよりも、保険で渡したほうが節税につながるケースがあります。
3. 配偶者の税額軽減を利用する
配偶者は、相続財産のうち法定相続分 or 1億6,000万円まで非課税となります。
そのため、一時的に配偶者に多く相続させることで、納税を先延ばしすることも可能です。
ただし、将来的に配偶者が亡くなったときに二次相続が発生するため、全体として税負担が増える可能性もあります。事前の設計が大切です。
4. 不動産を有効に活用する
現金を不動産に変えると、相続税評価額を圧縮できます。
特に、賃貸用の不動産は「貸家建付地」として評価が下がるため、相続税対策に有効です。
ただし、借入を伴う投資や空室リスクには注意が必要です。不動産は専門家との事前相談が必須です。
よく使われる相続税対策まとめ
| 方法 | 節税効果 | 注意点・ポイント |
|---|---|---|
| 生前贈与 | 年110万円まで非課税 | 贈与契約書の作成が望ましい |
| 生命保険の活用 | 非課税枠を活用して現金移転 | 相続人の人数で非課税枠が変わる |
| 配偶者の税額軽減 | 最大1億6,000万円まで非課税 | 二次相続の課税に注意 |
| 不動産の評価圧縮 | 現金より低い評価で節税可能 | 管理・空室・借金リスクがある |
よくある質問Q&A
Q1. 贈与は110万円以内なら何に使ってもいいの?
A. はい、自由に使えます。ただし、あくまで“贈与”であることが条件です。
名義預金や親が実質的に管理している場合などは、相続時に問題となることがあります。
Q2. 相続対策は何歳くらいから始めるのが良いですか?
A. 目安としては60歳前後から始めるのが理想です。
ただ、相続は「いつ起こるか分からない」からこそ、早めの準備が安心です。
まとめ:家族のために、今すぐできる相続税対策を
相続税は、「かからないようにする工夫」が事前に可能な税金です。
・生前贈与
・保険の活用
・不動産の活用
など、正しく準備を進めれば、家族に残せる財産は大きく変わります。
📞 税理士法人ビジョン・ナビでは、相続税対策の初回相談を無料で行っています。
「何から始めればいいかわからない…」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。

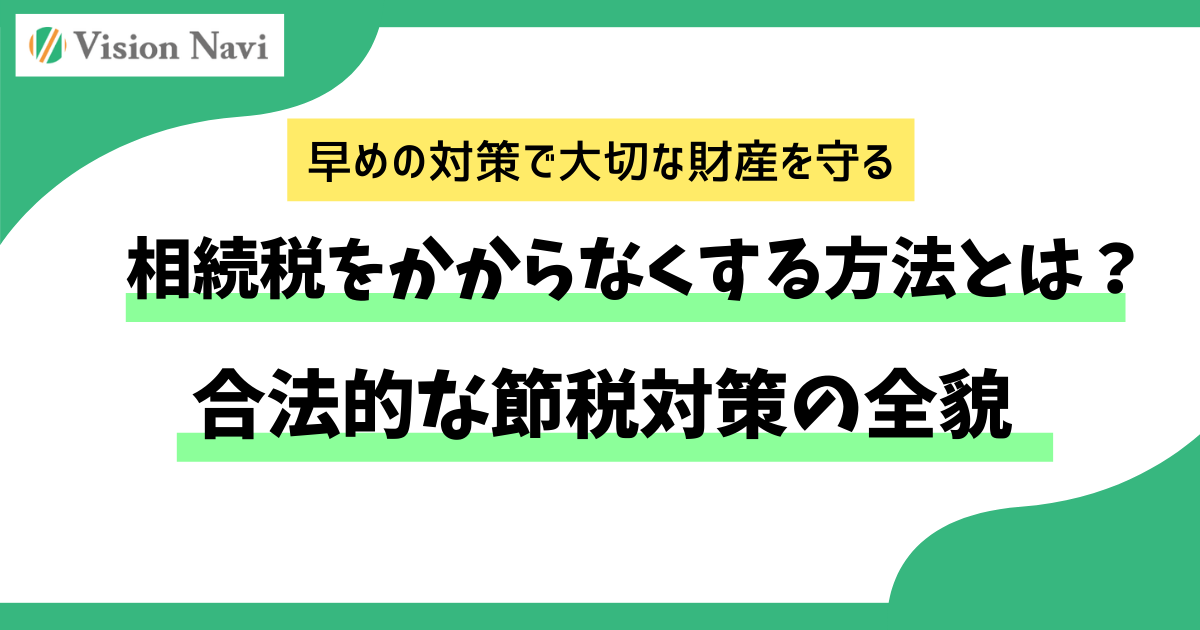
.png?width=750&name=%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%BF%E7%B6%99%20(1).png)

