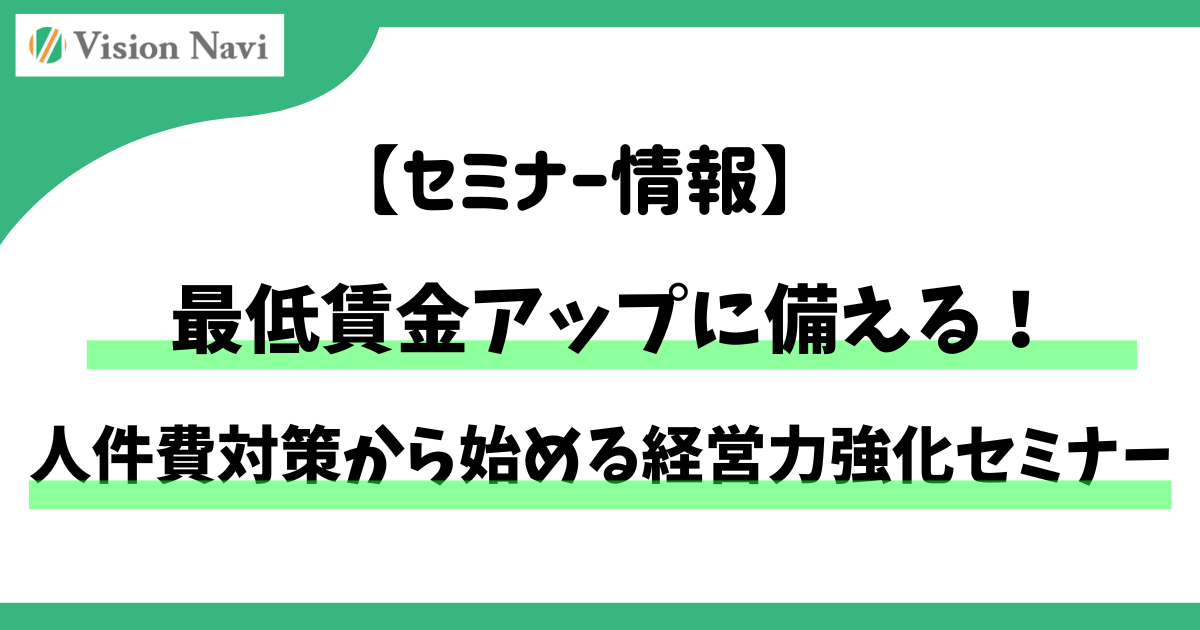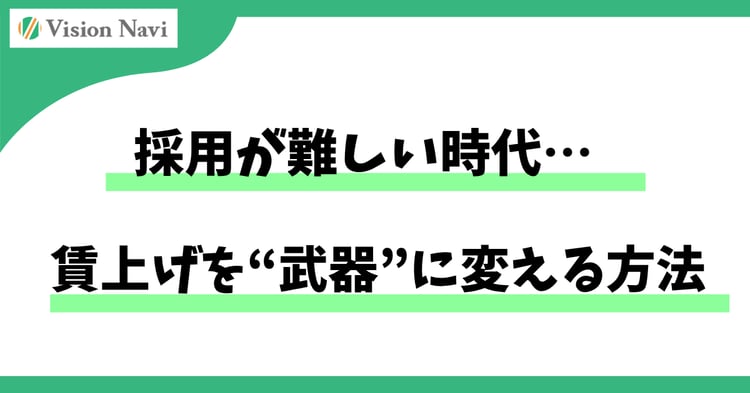最低賃金アップ、人件費のプレッシャーにどう備える?
近年、最低賃金の引き上げが毎年のように行われており、多くの中小企業・個人事業主の皆さまから「人件費の負担が重くなっている」「賃上げしたいが利益が不安」という声が聞かれます。
実際、人件費は固定費の中でも大きな割合を占めるため、少しの引き上げでも経営に与えるインパクトは少なくありません。しかし一方で、賃上げや待遇改善をしなければ、人材の確保・定着が難しくなるという現実もあります。
本記事では、最低賃金アップに備えて今からできる人件費対策と、利益を守る経営計画の立て方についてやさしく解説します。あわせて、税理士法人ビジョン・ナビが開催する無料セミナーもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
なぜ最低賃金アップが中小企業経営に大きな影響を与えるのか
人件費は企業経営の中で大きな固定費
人件費は、売上に関わらず毎月発生する固定費です。例えば10人規模の会社で1人あたり月給25万円の場合、最低賃金が上がれば、年間で数十万円単位の人件費増加が発生します。
中小企業では人件費率(売上に対する人件費の割合)が高い傾向があるため、少しの引き上げでも利益率を圧迫します。
賃上げは人材確保・定着のチャンスにも
一方で、賃金を適切に上げることは、優秀な人材の確保・定着につながります。人材不足が慢性化する中、賃上げをコストではなく投資と考える視点も必要です。
重要なのは、人件費を「戦略的にコントロール」することです。
今すぐ取り組める人件費対策の具体策
賃金規程・就業規則の見直し
まずは、自社の賃金規程や就業規則が現状に合っているか確認しましょう。
賃金体系が複雑であったり、成果と連動していなかったりすると、人件費が無駄に膨らみやすくなります。
規程の整理・明確化により、「どんな成果にいくら支払うか」を定義することで、人件費をコントロールしやすくなります。
評価制度・人事制度の構築
賃上げを単なる「横並び昇給」にしてしまうと、モチベーションが上がらず生産性も伸びません。
職務・成果・スキルに応じて給与を決める評価制度や人事制度を整えることで、限られた人件費で最大の成果を生む組織に近づけます。
人件費を織り込んだ経営計画が利益を守るカギ
人件費アップが利益に与える影響を見える化
賃上げを実施する前に、「人件費がいくら増えると利益がどうなるか」をシミュレーションしておくことが重要です。
粗利率・販管費・利益率のバランスを確認し、どの程度まで人件費を上げても利益が残るかを把握しておくと安心です。
必要売上高を逆算して計画を立てる
利益を守るためには、人件費を前提にした売上目標の逆算が欠かせません。
例えば「人件費を年200万円増やすなら、粗利率〇%の場合、追加で売上〇〇万円が必要」といった形で計算します。
このプロセスを税理士法人ビジョン・ナビでは支援しています。
最低賃金アップに備えるためのポイント整理
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の見直し | 賃金規程・就業規則を現状に合わせる |
| 生産性向上 | 業務効率化・IT活用で人件費当たりの成果を高める |
| 公平な制度 | 評価制度・人事制度を整備する |
| 経営計画 | 人件費を織り込んだ利益計画を立てる |
| 専門家活用 | 税理士・社労士・コンサルと連携して設計する |
よくある質問Q&A
Q1. 最低賃金アップに備えて、最初に何から着手すべきですか?
A. まずは人件費の「見える化」と賃金規程の見直しです。
自社の人件費構造を数値で把握したうえで、どの職種・役割にどの程度コストをかけているかを確認することが第一歩です。
Q2. 評価制度を導入するのに時間や費用はかかりますか?
A. 数か月単位で整備するのが一般的です。
制度設計は外部専門家と一緒に進めることで、自社だけで進めるより効率的かつ失敗も少なくなります。
まとめ:今こそ「制度」と「数字」で経営を守る時
最低賃金アップは避けられない流れです。しかし、「制度を整え」「数字で経営を考える」ことで、むしろ人件費を武器にする経営が可能になります。
税理士法人ビジョン・ナビでは、春日大樹氏(アクティブアンドカンパニー)と共催で
「最低賃金アップに備える!人件費対策から始める経営力強化セミナー」を開催します。
制度と数字の両輪を整えたい方は、ぜひご参加ください。
📩 セミナー詳細・お申し込みはこちら
【申込フォームURL】