こんにちは、税理士法人ビジョン・ナビです!
中小企業において、「人」に関するトラブルは避けて通れません。特に、労務トラブルが起きやすい会社には、共通する特徴があります。そして、そのような会社は税務面でもリスクを抱えていることが多いのです。今回は、労務トラブルが起きやすい会社の特徴と、そこに潜む税務的リスクの関係を解説します。
■ 労務トラブルが起きやすい会社の特徴
① 就業規則・労働契約書が整備されていない
就業規則が古いまま、または存在しない会社では、労働時間・残業・休日などのルールが曖昧になります。
結果として「言った・言わない」「そんな契約ではない」といったトラブルが発生しやすくなります。
② 給与計算や勤怠管理が属人的
手作業で給与を計算している、勤怠の打刻が不正確などのケースでは、未払い残業代や社会保険料の計上漏れが発生しがちです。
これが発覚すると、遡って支払いを求められるだけでなく、税務調査で経費処理の誤りとして指摘されることもあります。
③ 社内のコミュニケーション不足
経営方針が共有されていない、評価制度が不透明など、「不公平感」がトラブルの温床になります。
モチベーション低下や離職率の上昇だけでなく、税務的には退職金や給与の支給基準が曖昧になるなど、処理上のリスクにもつながります。
■ 労務トラブルと税務的リスクの関係
● 給与・残業代の未払いが経費認定されないケース
支給の実態が曖昧な給与や未払い残業代は、損金(経費)として認められないことがあります。
たとえば「支給額の根拠が不明」「帳簿や明細の裏付けがない」といった場合、架空人件費と認定されると、税務調査で否認され、追徴課税の対象になることも。
● 架空人件費や名義給与の誤解リスク
労務管理がずさんな会社では、役員家族に対する「名義だけの給与」や「実態のないボーナス」が発生しがちです。
これも税務署が厳しく見るポイントであり、役員報酬の損金否認などのリスクにつながります。
● 労務リスクが「税務調査のきっかけ」になることも
労働基準監督署(労基署)の調査と税務署の調査は、それぞれ別の目的で行われます。
ただし、労務上の問題が税務面に影響を及ぼすケースは少なくありません。
たとえば、未払い残業や賃金の誤った計算が発覚し、労基署から是正勧告を受けた場合。
その際、企業の帳簿や給与処理の整合性が注目され、税務署が「給与処理や源泉徴収が適正か」を確認する可能性もあります。
■ 労務トラブルを防ぎ、税務リスクを減らすために
-
就業規則・雇用契約書を最新化する
労基法改正や働き方改革に対応した内容へ見直しを行いましょう。 -
勤怠・給与をクラウド化して見える化する
手作業ではなく、データで一元管理することで証拠性が高まります。 -
税理士・社労士が連携する体制を整える
労務と税務は切り離せません。両方をカバーできる体制づくりが重要です。
■ まとめ:労務整備は「人」と「数字」を守る経営戦略
労務トラブルの多い会社は、同時に税務的リスクも高い傾向があります。
「うちは小さい会社だから大丈夫」と油断していると、後で高額な追徴税や未払い請求が発生することも。
税理士法人ビジョン・ナビでは、税務と労務の両面から“揉めない会社づくり”をサポートしています。
労務管理や経費処理に不安がある方は、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。
▼ 無料相談はこちらから
人と数字の両面から、安心できる経営体制を一緒に整えましょう。

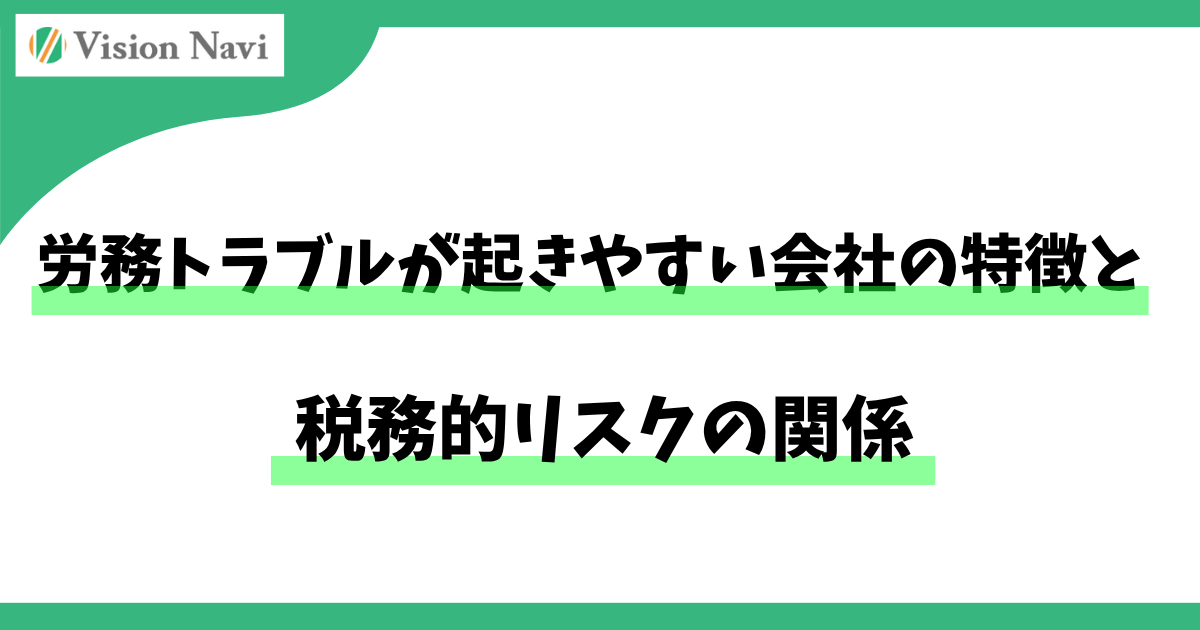
.png?width=750&name=%E7%B4%99%E3%81%AE%E7%B5%8C%E7%90%86%E3%81%8B%E3%82%89%20(1).png)

