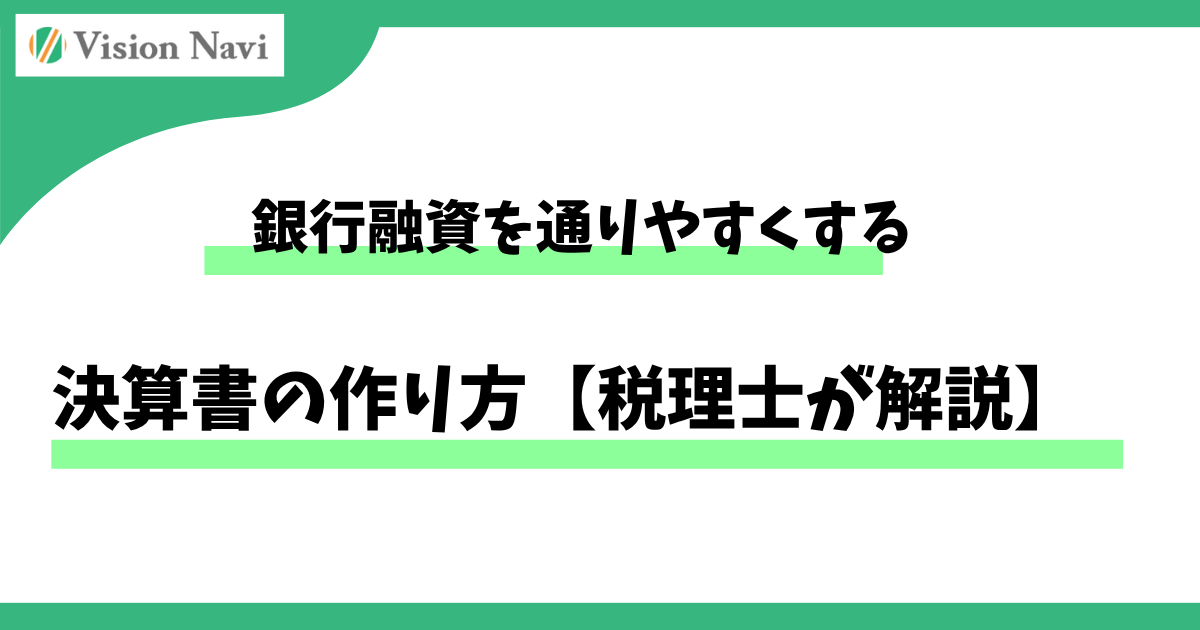融資が通らないのは「決算書の印象」が原因かも?
「売上は伸びているのに、なぜか融資が通らない…」
「銀行担当者に『決算内容をもう少し改善してください』と言われた…」
こうしたお悩みを持つ中小企業経営者・個人事業主の方は少なくありません。実は、銀行融資の審査では決算書の“中身”と“見せ方”の両方が重要です。
この記事では、税理士が実際の融資支援の現場で培った経験をもとに、銀行が信頼を寄せる決算書の作り方を分かりやすく解説します。
この記事を読めば、融資が通りやすい決算書のポイントが明確になり、次の融資申請を有利に進めることができます。
銀行が決算書でチェックしている3つのポイント
① 収益性(利益の安定性)
銀行は「返済能力」を見るために、まず利益の安定性を確認します。
赤字決算が続いていたり、売上が急減していると、返済リスクが高いと判断される可能性があります。
特に、営業利益や経常利益が安定しているかを重視されるため、経費の見直しや粗利率の改善が欠かせません。
② 財務健全性(自己資本比率)
自己資本比率とは、「会社がどれだけ自分のお金で事業を支えているか」を示す数値です。
この割合が高いほど、外部借入に依存せず、健全な財務体質と評価されます。
一方で、借入金が多く自己資本比率が低いと、「返済に余裕がない会社」と見られるリスクがあります。
③ キャッシュフロー(現金の動き)
黒字でも現金が足りなければ返済はできません。銀行は「利益よりもキャッシュフロー」を重視します。
そのため、日常的に資金繰り表を整備し、キャッシュの流れを見える化しておくことが重要です。
融資を通りやすくする決算書の作り方
① 経費の整理と「見せ方」の工夫
必要以上に経費を計上していると、利益が圧縮されて見え、返済能力が低く評価されます。
もちろん節税は大切ですが、「節税しすぎて融資に不利になる」ケースも少なくありません。
たとえば、私的な支出を経費に含めると、金融機関に「数字の信頼性に欠ける」と思われてしまいます。
決算時には、節税と融資評価のバランスを意識しましょう。
② 将来性を示す「事業計画書」を添付
金融機関は過去の実績だけでなく、将来の展望にも注目します。
決算書に加えて、事業計画書を添付することで「今後の成長戦略」や「資金使途の明確さ」を伝えられます。
税理士と一緒に、売上・利益・キャッシュフローの見通しを数値化することで、信頼度が大きく向上します。
③ 借入金の整理と返済実績の管理
複数の金融機関から借入がある場合は、返済スケジュールを明確に整理しましょう。
延滞や返済遅れがあると、審査に悪影響を与えます。
税理士と定期的に資金繰り表を確認し、返済状況を整えておくことが重要です。
税理士が教える「融資に強い決算書」作成のポイント整理
| チェック項目 | 対応内容 |
|---|---|
| 利益が安定しているか | 経費の見直し・無駄な支出削減 |
| 自己資本比率を改善できているか | 借入依存を減らし、内部留保を積み増す |
| キャッシュフローがプラスか | 資金繰り表を作成・運用 |
| 節税と融資評価のバランス | 税理士と相談しながら調整 |
| 事業計画書を添付しているか | 将来の成長戦略を具体的に示す |
この表をもとに自社の決算書を見直すことで、銀行の印象を大きく改善することができます。
よくある質問Q&A
Q1:赤字決算でも融資を受けられることはありますか?
A:はい。赤字でも「一過性の原因」「資金の使い道が明確」「黒字化への計画が現実的」など、再建の見込みがある場合は融資が通ることもあります。
特に事業計画書の内容がしっかりしていると、金融機関は前向きに評価します。
Q2:税理士に融資サポートを依頼するメリットは?
A:税理士は、決算書の信頼性を高める専門家です。
さらに、銀行とのやり取りに慣れており、融資のための資料作成・数値調整・面談対策までサポートできます。
自社だけで動くよりも、はるかにスムーズに審査を進められます。
まとめ:信頼される「決算書」で、融資をスムーズに
銀行融資は「数字の信頼性」と「将来性」を見せる戦いです。
そのカギを握るのが、正確で戦略的な決算書です。
税理士法人ビジョン・ナビでは、
-
銀行が重視する決算書の改善
-
融資面談対策
-
事業計画書の作成支援
を通じて、中小企業の資金調達をトータルサポートしています。
融資でお悩みの方は、まずは無料相談をご利用ください。
→ 無料相談はこちら