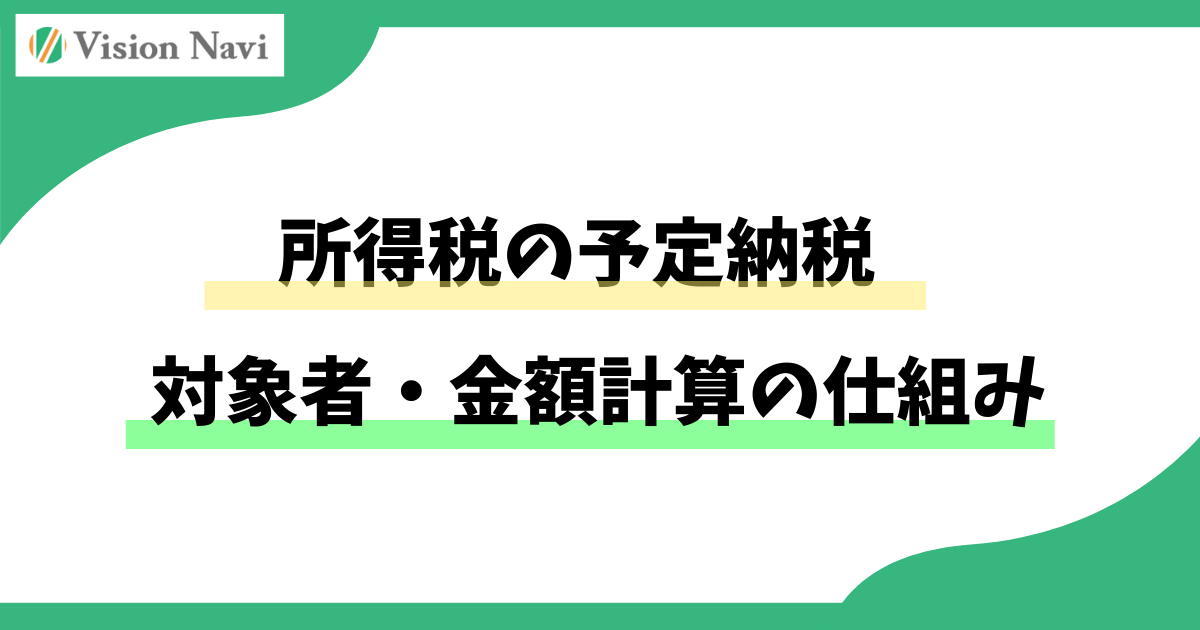「予定納税」という通知が税務署から届いて戸惑った経験はありませんか?
特に中小企業経営者や個人事業主の方は、「なぜ自分に届いたのか」「いくら支払う必要があるのか」と疑問に感じるケースが多いようです。
本記事では、所得税の予定納税の対象者・金額の計算方法・仕組みをわかりやすく解説します。最後まで読めば、「自分は対象になるのか?」「納税額はどう決まるのか?」を理解し、安心して対応できるようになるはずです。
所得税の予定納税とは?
予定納税の基本
予定納税とは、翌年の確定申告で支払う所得税を、前もって分割して納める制度です。
前年の所得税額を基準に計算され、原則として 7月と11月の2回 に分けて納付します。
もし予定納税がなければ、確定申告の時期に数十万円単位の税金をまとめて納めることになり、資金繰りに大きな負担を与えてしまいます。そのため、予定納税は「納税者の負担を分散する制度」として位置づけられています。
精算の仕組み
翌年の確定申告時に実際の所得税額と比較し、
-
払いすぎていれば「還付」
-
足りなければ「追加納付」
という形で調整されます。
👉 詳細は国税庁|予定納税でも確認できます。
予定納税の対象者は誰?
対象となる条件
予定納税はすべての人が対象になるわけではありません。以下の条件を満たす場合に適用されます。
-
前年の確定申告で納めた 所得税額が15万円以上 である
-
主に 個人事業主・不動産所得者・副業収入がある人 が該当する
中小企業経営者や個人事業主の方は、前年に利益が出ていれば対象になる可能性が高いといえます。
不要となるケース
-
前年の所得税額が15万円未満
-
退職などで今年の所得が大きく減る見込み
-
災害など特別な事情で収入が減少する場合(減額申請が可能)
予定納税の金額計算の仕組み
計算方法
予定納税額は、原則として 前年の確定申告で納めた所得税額の3分の1 ずつを2回に分けて納付します。
【例】前年の所得税額が30万円の場合
-
第1期(7月納付):10万円
-
第2期(11月納付):10万円
-
翌年の確定申告で残り10万円と精算
注意点
-
所得税の「基準額」は「申告納税額-源泉徴収額」などを基に計算されます。
-
事業の利益が大きく変動する場合は、「減額申請」により納税額を減らすことが可能です。
ポイント整理
-
✅ 所得税の予定納税は「前払いの仮納税」制度
-
✅ 前年の所得税が15万円以上の人が対象
-
✅ 7月と11月の2回に分けて支払う
-
✅ 翌年の確定申告で過不足を精算
-
✅ 業績悪化時は「減額申請」が可能
よくある質問Q&A
Q1. サラリーマンでも予定納税の対象になるの?
A. 給与所得だけの方は基本的に対象外です。ただし、副業収入や不動産収入がある場合には予定納税が必要になることがあります。
Q2. 予定納税を忘れたらどうなる?
A. 納付期限を過ぎると 延滞税 が発生します。気づいた時点ですぐに納付すれば負担を最小限に抑えられます。
Q3. 今年は利益が減っているのに前年ベースで計算されてしまう…
A. その場合は「予定納税の減額申請」が可能です。収入減の理由を添えて申請すれば、予定納税額を減らすことができます。
まとめ|予定納税を正しく理解して安心経営へ
所得税の予定納税は、前年の所得税額を基準に「分割前払い」する仕組みです。
対象者や金額計算の流れを理解しておくことで、資金繰りの不安を減らし、計画的な納税が可能になります。
税理士法人ビジョン・ナビでは、予定納税の金額確認・減額申請・資金繰りに関する無料相談を承っています。
「自分はいくら納めるのか?」「減額できるのか?」と疑問のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。