「想い」は伝わる。でも、「数字」でつまずく。
こんにちは、税理法人ビジョン・ナビです!
京都の経営者の方々の中には、
「そろそろ後継者に会社を任せたい」と考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし、実際の現場では――
「兄弟間で株式の分け方でもめた」
「会社の資産がどこまでなのか分からない」
「決算書を見ても、どこが問題なのか分からない」
といったトラブルが数多く発生しています。
その原因の多くは、“数字の整理不足”にあります。
つまり、感情や立場の問題ではなく、「見える化されていない数字」が争いの火種になるのです。
この記事では、京都で数多くの事業承継を支援してきた
税理士法人ビジョン・ナビが、事業承継で揉めないための「数字整理術」を具体的に解説します。
なぜ事業承継は“数字”でもめるのか?
① 会社の資産が整理されていない
中小企業では、経営者個人と会社のお金が混ざっているケースが少なくありません。
たとえば、次のような状態です:
-
経営者名義の不動産を会社で使用している
-
会社の口座からプライベートな支払いをしている
-
退職金・借入金・保証債務の扱いが不明確
このまま承継すると、「どこまでが会社の資産か」「誰に何を引き継ぐか」が不明瞭となり、
親族間トラブルや税務リスクを招くおそれがあります。
② 自社株の評価を知らないまま進めている
事業承継で最も重要なのが自社株の評価額です。
ところが、「うちの株は価値がない」と思い込んでいる経営者が非常に多いのが実情。
実際には、会社の利益や純資産が一定水準を超えると、
株価が高く算定され、相続税や贈与税の負担が数千万円単位になることもあります。
京都の老舗企業や資産型企業では特にこの傾向が強く、
「知らないまま贈与して高額課税」という事例も少なくありません。
③ 経営数字を後継者が理解していない
経営のバトンタッチは、「代表権」だけでは不十分です。
後継者が会社の財務構造や利益の仕組みを理解していなければ、
承継後に資金繰り悪化や経営判断の遅れを招くリスクがあります。
つまり、事業承継とは「経営者の想い」だけでなく、
数字を通じた経営感覚の承継でもあるのです。
揉めないための“数字整理術”3ステップ
① 財産と負債の「棚卸し」を行う
まず最初に行うべきは、会社と個人の財産・負債を明確に分けることです。
| 整理すべき項目 | チェックポイント |
|---|---|
| 不動産 | 名義・使用目的・評価額を確認 |
| 預金・現金 | 個人口座と会社口座を明確に分離 |
| 借入金 | 保証人の有無・返済計画を整理 |
| 保険 | 契約者・受取人・目的を確認 |
この整理をすることで、「引き継ぐ資産」と「引き継がない資産」が明確になります。
税理士が入ることで、相続税・贈与税の観点からも最適な区分を提案できます。
② 自社株の評価を正確に把握する
次に、自社株式の評価を行いましょう。
評価方法には「類似業種比準方式」や「純資産方式」などがあり、
会社の規模や業種によって算出結果が大きく異なります。
たとえば、同じ年商でも以下のような差が出ることがあります:
| 会社タイプ | 評価方式 | 株価の目安 |
|---|---|---|
| 赤字続きの製造業 | 純資産方式 | 低評価(税負担軽い) |
| 安定黒字の老舗企業 | 類似業種比準 | 高評価(税負担大) |
このように、自社株の価値を知らずに承継すると、
思わぬ税金が発生するリスクがあるため、事前の試算が必須です。
③ 数字を共有できる「後継者会議」を開く
数字整理の最終ステップは、後継者と数字を共有する時間を持つことです。
税理士法人ビジョン・ナビでは、
-
月次決算の読み方研修
-
損益分岐点の把握方法
-
経営計画と資金繰りの見える化
といったサポートを通じて、後継者が“数字で経営を語れる力”を身につけるお手伝いをしています。
これにより、「数字の見えない経営」から「数字で判断する経営」へと変化し、
承継後の安定した運営が可能になります。
数字整理を怠ると起こりやすいトラブル例
| トラブル内容 | 発生原因 | 防止策 |
|---|---|---|
| 親族間での株式争い | 自社株評価が不明確 | 税理士による株価試算と分割設計 |
| 承継後の資金繰り悪化 | 財務構造の理解不足 | 後継者への数字教育 |
| 不当な税負担 | 相続・贈与の計画不足 | 事前シミュレーションと節税策 |
これらはすべて、“数字整理の不足”が原因です。
逆に言えば、数字を整理し、見える化しておくだけで、ほとんどのトラブルは防げます。
よくある質問(Q&A)
Q1:事業承継の準備は何年前から始めればよいですか?
A:理想は5〜10年前です。
特に株式や不動産の名義変更、贈与対策は長期的に行うことで節税効果が高まります。
Q2:後継者がまだ若く、経営を任せるのが不安です。
A:段階的な承継(部分譲渡・共同経営期間)を設ける方法もあります。
税理士が関与することで、数字と実務の両面から安全な移行をサポートできます。
「数字を整えること」が、家族と会社を守る第一歩
事業承継は、「想い」と「数字」の両輪で進めることが大切です。
どちらかが欠けると、せっかく築いた会社が混乱やトラブルに巻き込まれてしまうこともあります。
税理士法人ビジョン・ナビでは、京都の企業の実情に合わせた
“数字から始める事業承継支援”を行っています。
-
自社株評価・贈与税シミュレーション
-
財産棚卸と節税提案
-
後継者向け経営数字トレーニング
を通じて、安心して「想い」と「数字」をつなぐお手伝いをいたします。
👉 【無料相談はこちら】事業承継・数字整理サポートを予約する(お問い合わせフォーム)
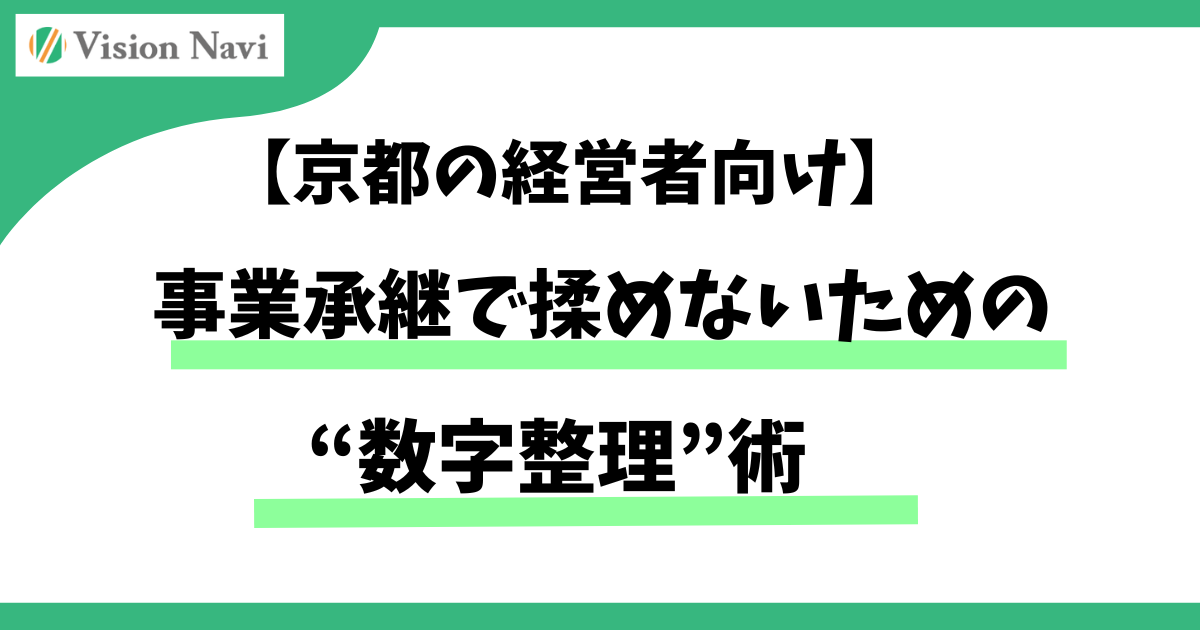

.png?width=750&name=%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%BF%E7%B6%99%20(2).png)