こんにちは、税理士法人ビジョン・ナビです!
「相続税の申告って、いくらくらいかかるの?」「税理士に頼むと高いのでは…?」
相続が発生した際、こうした疑問や不安を感じる方は多いのではないでしょうか。相続税の申告は、自分で行うこともできますが、税額の計算や財産評価など専門知識が必要なため、ミスがあると追徴課税のリスクもあります。
この記事では、税理士に相続税申告を依頼する際の費用相場と、注意しておきたいポイントをわかりやすく解説します。読めば、安心して依頼先を選ぶための判断基準がつかめます。
相続税申告を税理士に依頼するメリット
専門知識で正確な申告ができる
相続税の申告は、相続財産の評価、各種控除の適用、書類作成など非常に複雑です。税理士に依頼すれば、法令に基づいた正確な計算ができ、余計な税負担やペナルティを防げます。
節税の提案が受けられる
経験豊富な税理士なら、相続人ごとの節税対策や分割方法の提案も可能です。単に申告書を作成するだけでなく、家族の今後を見据えたトータルサポートが受けられる点が大きなメリットです。
期限内に安心して手続きできる
相続税の申告期限は「相続開始から10か月以内」と限られています。慣れない手続きをご自身で進めると時間がかかりすぎることも。税理士に任せることで、スケジュール管理も含めて安心して対応できます。
相続税申告の費用相場はどのくらい?
一般的な相場感
相続税申告を税理士に依頼する場合、費用は30万円〜100万円前後が一般的な目安です。
ただし、財産の種類・評価額・相続人の人数などによって金額は大きく変わります。
| 財産規模 | 費用相場(税別) |
|---|---|
| 3,000万円未満 | 約30〜40万円 |
| 5,000万円前後 | 約50〜70万円 |
| 1億円前後 | 約70〜100万円 |
| 2億円以上 | 100万円以上〜 |
不動産が多いケースや、複数の相続人間で揉めているケースでは、財産評価の作業量が増えるため、追加料金が発生することもあります。
費用に含まれる主な業務内容
-
財産の調査・評価
-
各種控除の適用検討
-
相続税申告書の作成
-
申告書提出代行
-
税務調査対応(オプションの場合あり)
税理士に依頼する際の注意点
① 「料金体系」が明確な事務所を選ぶ
見積もり時に、基本報酬と追加料金の条件を明確に説明してくれるかを確認しましょう。中には、「土地評価1件ごとに追加費用」「戸籍謄本などの取得代行費別途」といった条件がある場合も。
② 相続税専門の経験があるか確認する
相続税は、所得税や法人税とは異なる専門知識が必要です。
過去の申告実績が豊富な税理士なら、税務署との対応や節税提案もスムーズです。
③ 節税提案の有無を見る
単に「申告書を作るだけ」ではなく、生前贈与や不動産の活用などのアドバイスをしてくれるかどうかも重要。将来を見据えた提案があるか確認しましょう。
相続税申告依頼のポイントまとめ
-
費用相場は 30〜100万円前後
-
財産規模や不動産の有無で金額は変動
-
経験豊富で料金体系が明確な税理士を選ぶ
-
節税提案までしてくれる事務所が安心
よくある質問(Q&A)
Q1. 相続税申告を自分で行うことはできますか?
A. 可能ですが、財産評価や控除の判断を誤ると追徴課税のリスクがあります。複数の土地や非上場株式を含む場合は、専門家に依頼するのが安全です。
参考:[国税庁|相続税の申告書の書き方]
Q2. 税理士報酬は相続税の経費になりますか?
A. 相続税の申告にかかる税理士報酬は、被相続人の債務控除には該当しません。ただし、遺産分割協議に関する費用など、目的によって扱いが異なる場合があります。
まとめ:費用を理解し、信頼できる税理士に相談を
相続税申告を税理士に依頼する際は、費用相場だけでなく、対応の丁寧さ・節税提案の有無・実績なども重要な判断基準です。
ビジョン・ナビでは、初回のご相談を無料で承っております。費用の目安や相続手続きの流れを丁寧にご説明いたします。
「うちのケースだと、どれくらいの費用になりそう?」
そんな疑問もお気軽にご相談ください。
▶︎【無料相談はこちら】

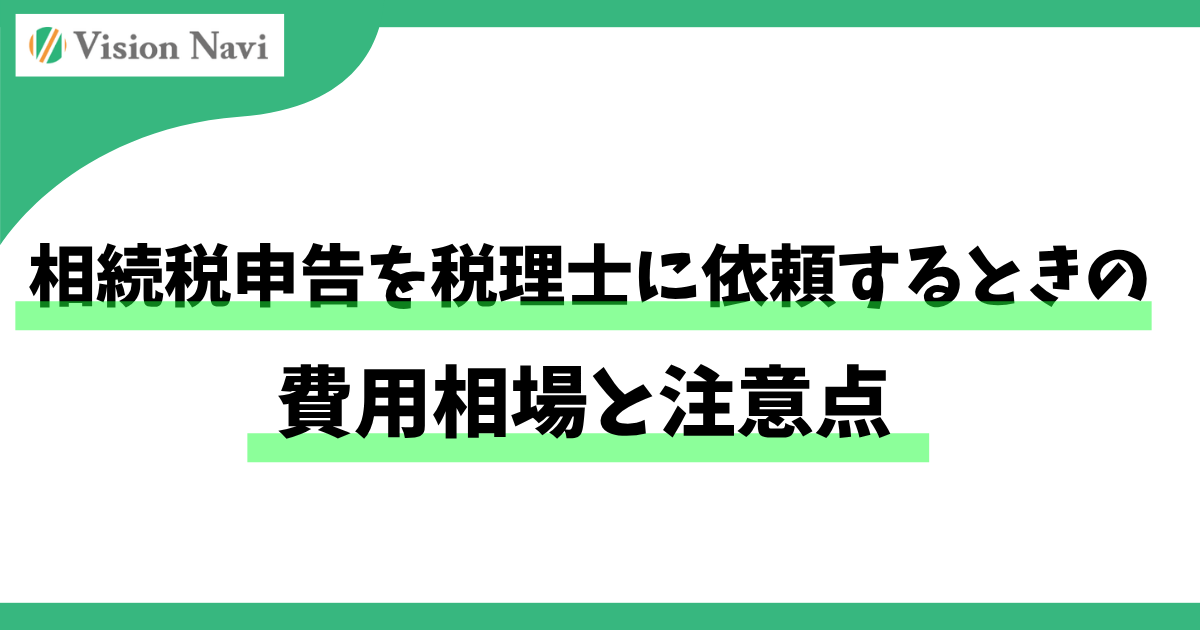
.png?width=750&name=%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%BF%E7%B6%99%20(1).png)

