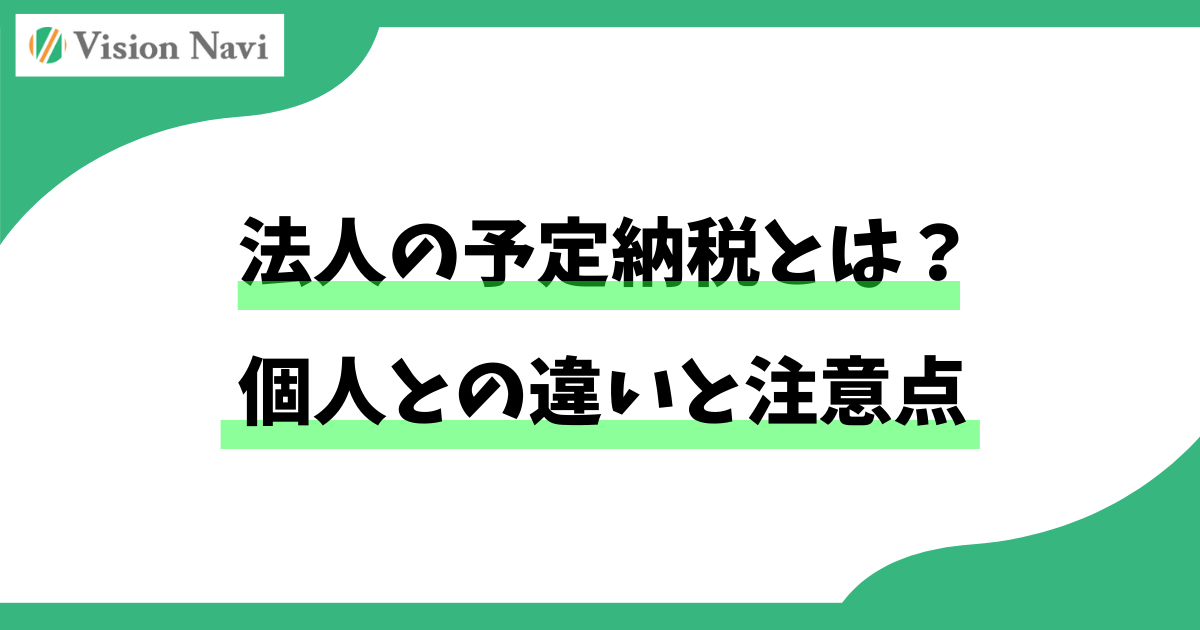こんにちは、税理士法人ビジョン・ナビです!
「予定納税」と聞くと、個人事業主やフリーランスが対象だと思われがちですが、実は法人にも予定納税の制度があります。
中小企業の経営者にとっては、法人の予定納税を理解していないと、思わぬ資金繰りの悪化や延滞税のリスクにつながることもあります。
この記事では、法人における予定納税の仕組み・個人との違い・注意点をわかりやすく解説します。最後まで読むことで、自社の納税スケジュールを把握し、安心して経営に集中できるようになるはずです。
法人の予定納税とは?
基本の仕組み
法人の予定納税とは、法人税をあらかじめ中間で前払いする制度です。
法人税の納税は、原則として事業年度終了後に確定申告をしてから納めます。しかし、1年間待ってまとめて支払うと国の税収が偏ってしまうため、事業年度の途中で仮に納める仕組みが設けられています。
対象となる法人
法人の予定納税(中間申告)が必要なのは、次の条件を満たす場合です。
-
前事業年度の法人税額が 20万円超 の法人
この場合、事業年度の途中(原則として開始から6か月後)に予定納税を行う必要があります。
個人の予定納税との違い
予定納税は「個人」と「法人」で仕組みが異なります。違いを整理すると以下の通りです。
| 項目 | 個人の予定納税 | 法人の予定納税 |
|---|---|---|
| 対象税目 | 所得税 | 法人税 |
| 基準となる金額 | 前年の所得税額15万円以上 | 前事業年度の法人税額20万円超 |
| 納付回数 | 原則2回(7月・11月) | 原則1回(事業年度の6か月経過後)※申告方式による |
| 精算方法 | 翌年の確定申告で精算 | 決算申告で精算 |
👉 個人は年に2回前払いし、確定申告で調整。法人は基本的に1回の中間納付で、決算申告で精算する点が大きな違いです。
法人の予定納税の方法
法人の予定納税には、大きく分けて2つの方法があります。
① 前年度実績による申告(予定申告方式)
前事業年度の法人税額を基準に計算し、その 2分の1を中間申告・納付 します。
【例】前年度の法人税額が40万円の場合
→ 中間申告として20万円を納付
② 仮決算による申告(仮決算方式)
事業年度の中間時点で決算を組み、実際の所得に基づいて税額を計算・申告する方法です。
赤字の場合や利益が減少している場合には、この方式を選ぶことで予定納税額を抑えられるメリットがあります。
法人の予定納税で注意すべきポイント
資金繰りへの影響
予定納税は事業年度の途中で発生するため、資金繰りに与える影響は大きいです。特に、売上の波がある業種では「思わぬ時期に多額の納税が必要」となりやすいので、事前に納税資金を確保しておくことが重要です。
仮決算方式の検討
前年度に利益が大きく出たが、当年度は減少している場合には、予定申告方式で納税すると払いすぎになってしまいます。そうした場合は仮決算方式を活用して、予定納税額を調整するのがポイントです。
期限を守ること
予定納税を忘れたり遅れたりすると、延滞税や加算税が発生します。法人税の納付期限は厳格に管理されているため、経理担当者や顧問税理士とスケジュールをしっかり確認しましょう。
よくある質問Q&A
Q1. 中小企業でも法人の予定納税は必要?
A. はい。前事業年度の法人税額が20万円を超えていれば、中小企業でも予定納税が必要になります。規模の大小に関わらず適用される点に注意してください。
Q2. 資金繰りが厳しい場合、法人の予定納税を減らす方法はある?
A. 仮決算方式を選ぶことで、実際の利益に基づいた税額で申告できます。赤字や利益減の場合には納税額を抑えられるため、顧問税理士と相談して検討すると良いでしょう。
まとめ|法人の予定納税は計画的な資金管理がカギ
法人の予定納税は、法人税を前払いする制度であり、前年度の法人税額が20万円を超える場合に発生します。
-
個人は「所得税」、法人は「法人税」が対象
-
個人は2回払い、法人は原則1回(中間納付)
-
法人は「予定申告方式」と「仮決算方式」が選べる
中小企業経営においては、予定納税は資金繰りに大きな影響を与えます。制度を理解し、早めの資金準備や仮決算方式の検討を行うことが大切です。
税理士法人ビジョン・ナビでは、法人の予定納税額の試算や仮決算のサポート、資金繰り対策の無料相談を承っています。気になる方はお気軽にご相談ください。