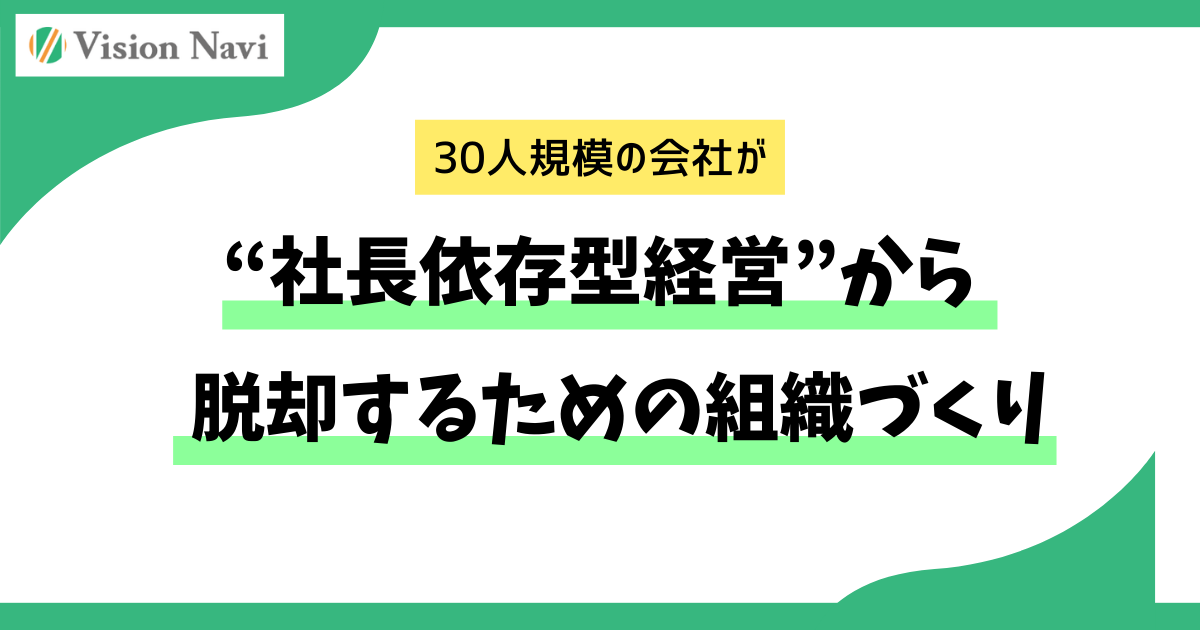こんにちは、税理士法人ビジョン・ナビです!
「社員が育たず、何でも社長に聞いてくる」
「社長が現場を回さないと会社が止まってしまう」
そんな“社長依存型経営”に悩む中小企業は少なくありません。特に社員30人前後の規模では、社長の意思決定がすべてに影響する一方、組織体制が整わずに限界を迎えるケースが目立ちます。
この記事では、30人規模の会社が社長依存型経営から脱却するための具体的な組織づくりの方法を解説します。
なぜ中小企業は“社長依存型”になりやすいのか?
-
社員数が少なく、役割分担があいまいになりがち
-
権限移譲をしないまま、社長が業務を抱え込む
-
「社長の判断が一番早い」と社員も依存してしまう
この状態を放置すると、社長が倒れたときに会社が立ち行かなくなるリスクがあります。
👉 中小企業庁も、持続的成長には経営の属人化を防ぐ体制整備が不可欠と指摘しています(中小企業庁:経営支援)。
脱却のステップ① 権限移譲と役割の明確化
まず取り組むべきは「権限移譲」です。
-
部門ごとに責任者を配置する
-
業務フローを文書化し、誰が見ても分かる状態にする
-
社長は最終承認のみ、細かい判断は現場に任せる
これにより、社長の業務負担は減り、社員が自律的に動ける環境が生まれます。
脱却のステップ② ミドルマネジメントの育成
30人規模の企業では、課長・リーダー層が組織の要となります。
-
定期的にマネジメント研修を実施
-
会議の進行や部下指導を任せる
-
失敗してもフォローしながら経験を積ませる
管理職不足は多くの中小企業が抱える課題ですが、計画的に育成することで社長の右腕となる人材が育ちます。
👉 厚生労働省も「人材育成・キャリア支援」のため、様々な助成金制度を設けております。(厚生労働省:人材育成支援)。
脱却のステップ③ 情報共有の仕組みづくり
社長依存型の会社では「情報が社長にしかない」ことが大きな問題です。
-
社内ミーティングで情報をオープンにする
-
クラウドツールを活用し、業務データを共有
-
経営数字も可能な範囲で社員に開示
こうした仕組みによって、社員一人ひとりが経営に関心を持ち、主体的に行動できる組織へ変わります。
脱却のステップ④ ビジョンと価値観の浸透
社長の判断基準を社員が理解していないと、結局は「社長の指示待ち」になってしまいます。
-
経営理念やビジョンを定期的に共有する
-
行動指針を明文化し、評価制度にも反映する
-
社長だけでなく管理職が発信役となる
これにより、組織としての意思決定の軸が生まれ、社長不在でも動ける会社になります。
成功事例:30人規模の建設会社の場合
課題
・現場の判断はすべて社長が行い、業務が滞っていた。
改善内容
-
各現場にリーダーを配置し、権限を委譲
-
週1回の管理職ミーティングで情報共有
-
経営理念を再策定し、社内研修を実施
成果
・社長の稼働時間が月40時間削減(自己認識による時間数)
・リーダー層の主体性が高まり、離職率も低下
・新規案件への対応力が向上し、売上も伸長
よくある質問(Q&A)
Q1. 権限を渡すとミスが増えませんか?
A. 最初はミスも起こりますが、育成のチャンスと捉えましょう。失敗をフォローしつつ任せることで、成長スピードは加速します。
Q2. 30人規模で管理職を育てる余裕がありません…
A. 外部研修や専門家のサポートを活用するのも有効です。小さなステップから始めることがポイントです。
まとめ|社長依存から組織経営へ
30人規模の会社が成長を続けるには、社長のワンマン体制から組織で動く体制へ移行することが不可欠です。
権限移譲・マネジメント育成・情報共有・ビジョン浸透を進めることで、持続可能な組織がつくられます。
税理士法人ビジョン・ナビでは、経営体制の見直しや人材育成支援について無料相談を行っています。お気軽にお問い合わせください!