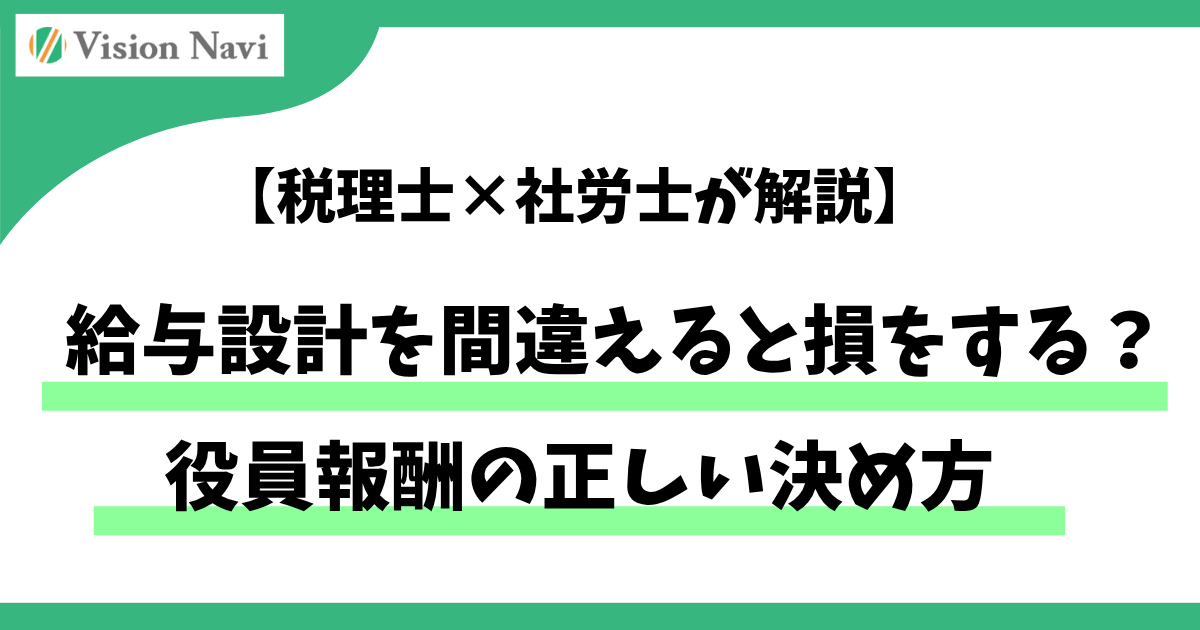こんにちは、税理士法人ビジョン・ナビです!
中小企業の経営者にとって、「役員報酬をいくらにすべきか」は永遠のテーマです。
「できるだけ節税したい」「社会保険料を抑えたい」と思っても、安易な設定が“損”につながることもあります。
この記事では、税理士と社労士の視点から、役員報酬の正しい決め方と注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
役員報酬を間違えると起こる3つの“損”
① 税金で損をする
役員報酬が高すぎると、所得税・住民税の負担が増加します。
一方で低すぎると、法人の利益が残りすぎて法人税の負担が重くなることも。
つまり、法人税と所得税のバランスが取れていないと、結果的にトータルで損をするのです。
② 社会保険料で損をする
社会保険料は報酬額に比例して増減します。
役員報酬を高く設定しすぎると、年間数十万円単位で負担が増えることもあります。
また、複数の役員がいる場合、トータルでの保険料負担を把握せず決定している企業も少なくありません。
③ 銀行融資で損をする
「節税のために報酬を低く抑えたら、銀行からの評価が下がった」というケースもあります。
金融機関は役員報酬を「経営者の生活実態」や「事業の安定性」の指標として見ているため、
過度に低い設定はマイナスに働くことがあります。
税理士×社労士が教える「正しい役員報酬の決め方」
1. 法人税・所得税・社会保険料の“総合最適”を考える
役員報酬の設計は、税金と社会保険料のバランス設計が鍵です。
法人税を抑えようと報酬を上げると所得税が増え、逆に下げると法人税が増える——。
その中間点を見極めることが重要です。
→ 税理士は「法人税・所得税のトータル最適化」、
社労士は「社会保険料・労務リスクの管理」の両面からサポートします。
2. 役員報酬は“期首3か月以内”に確定が原則
税務上、役員報酬は**「事業年度開始後3か月以内」に決定しなければ損金にできません。**
たとえ業績が好調でも、途中で増額するとその分は損金算入できず課税対象になります。
→【ポイント】
役員報酬は「事業計画」「業績見通し」「資金繰り」を踏まえて慎重に決定しましょう。
3. 将来の社会保険・年金も見据える
短期的な節税だけでなく、将来の年金受給額や退職金額にも影響します。
報酬を下げすぎると、老後の年金額が減る可能性もあるため、長期的な視点が欠かせません。
よくある質問(Q&A)
Q1. 役員報酬を途中で変更したい場合はどうすればいい?
A. 原則として、事業年度途中の変更はできません。ただし、代表交代や職務内容の変更など「やむを得ない事情」があれば認められる場合もあります。
Q2. 役員報酬と賞与を組み合わせることはできますか?
A. 「事前確定届出給与」として届出を出せば可能です。ただし、届出期限や金額の変更制限があるため注意が必要です。
まとめ:税金・社会保険・融資、すべてを見据えた給与設計を
役員報酬の設定は、「税金」だけを見て決めると失敗します。
税理士と社労士の両視点で“トータル最適化”することが最大のポイントです。
税理士法人ビジョン・ナビでは、
法人税・所得税・社会保険料を総合的に分析し、最も損をしない給与設計をサポートしています。
「今の役員報酬は妥当?」と感じたら、ぜひ無料相談をご利用ください。