導入文:決算直前、こんなお悩みありませんか?
「今年の利益が思ったより出そうで、法人税が心配…」
「節税をしたいけど、どこから手をつければいいのかわからない」
京都の中小企業経営者の皆さま、こんな不安を感じたことはありませんか?
決算前の数週間は、税金を抑える最後のチャンスです。とはいえ、無理な節税やグレーな処理は後々トラブルのもと。
この記事では、「合法的かつ実践的にできる節税対策」を10項目に分けて紹介します。
読むことで、決算前に取るべき行動が明確になり、会社のお金を守る具体的なヒントが得られます。
役員報酬の見直しでバランスを最適化
利益と報酬のバランスを調整
役員報酬は、会社の利益を圧縮しつつ、経営者個人の所得税を抑える節税ポイントです。
ただし、「定期同額給与」のルールに従っていないと損金算入できません。
決算前に「来期の報酬をいくらに設定するか」を税理士と相談しておくことが重要です。
賞与支給による調整も選択肢
役員賞与は原則として損金算入できませんが、「事前確定届出給与」に該当すれば可能です。
届出期限(期首から4か月以内)を過ぎていないか確認しましょう。
👉 詳細は国税庁「事前確定届出給与に関する手続」を参照。
経費計上の漏れを防ぐ
小口経費を見逃さない
交際費や消耗品費など、意外と漏れやすい経費を今一度チェック。
領収書がないものでも、少額であればメモを残しておくと証拠になります。
交際費の上限を確認
中小法人の場合、年間800万円までの交際費が損金算入可能です(飲食代なら50%まで)。
この上限を意識して、無駄なく経費処理を行いましょう。
資産の除却・廃棄を検討する
使っていない資産は早めに処分
古い設備や棚卸資産など、使っていないものは除却損として経費化できます。
物理的に廃棄し、写真などの証拠を残しておくことが大切です。
修繕費との違いに注意
改良や機能追加は資本的支出(資産計上)ですが、維持・修理は修繕費(経費)になります。
どちらに該当するか、税理士と判断を共有しておくと安心です。
在庫調整で適正な利益計上を
実地棚卸を徹底
在庫が多いと利益が膨らむため、期末在庫の評価は慎重に。
破損・劣化品があれば評価減の対象となる可能性があります。
原価計算の方法も確認
定額法・移動平均法など、在庫評価法は選択制。変更には届出が必要なので、長期的な視点で最適化しましょう。
節税型保険の活用は慎重に
保険による節税は「目的」で判断
かつて流行した「全損型保険」は現在制限されています。
加入する場合は「保障目的」が明確なものを選び、解約返戻金の扱いを理解しておきましょう。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
掛金の全額が損金算入できる有効な制度。最大800万円まで積立可能で、節税と資金繰りの両立ができます。
賞与・退職金の支給タイミングを見直す
支給日を決算月内に設定
社員への賞与は、支給日を決算期内に設定すれば経費計上可能です。
ただし、支給額と支給日が確定している必要があります。
退職金準備も検討
退職金制度を導入していない場合、将来的な支出に備えて「退職給与引当金」の積立も有効です。
固定資産の減価償却を再確認
償却方法と耐用年数を確認
減価償却費は毎期の利益を左右する大きな要素です。
特別償却や少額減価償却資産(30万円未満)制度も活用できます。
リース資産にも注意
リース契約によっては資産計上が必要な場合があります。契約内容を今一度確認しておきましょう。
福利厚生費を上手に活用
節税しながら社員満足度アップ
社員旅行、健康診断、慶弔見舞金などは福利厚生費として損金算入できます。
ただし、全社員が対象であることが条件です。
特定の社員だけの支給は注意
個人的な贈答などは「給与」として扱われる可能性があります。公平性を保ちましょう。
研究開発費・IT投資による優遇措置
税額控除制度を活用
研究開発税制や中小企業経営強化税制では、設備投資や開発費の一部を税額控除できます。
京都府内の製造・IT企業には特にメリットがあります。
IT導入補助金もチェック
クラウド会計や勤怠管理システムの導入は、国の補助金対象になる場合も。
節税+補助金のダブル効果を狙いましょう。
繰延資産・引当金を整理する
開業費や創立費の償却
未償却の繰延資産が残っていないか確認し、償却漏れがないように。
これも節税の一部です。
貸倒引当金の設定も有効
取引先に不安がある場合、貸倒引当金を計上しておくことで将来の損失に備えられます。
ポイント整理(まとめ表)
| 区分 | 節税ポイント | 概要 |
|---|---|---|
| 人件費関連 | 役員報酬・賞与 | 損金算入の条件を満たす |
| 経費関連 | 経費漏れ・交際費 | 上限800万円を活用 |
| 資産関連 | 除却・減価償却 | 証拠を残すことが重要 |
| 制度活用 | 共済・税額控除 | 国の制度を上手に使う |
よくある質問Q&A
Q1. 決算直前でも間に合う節税はありますか?
A. 経費計上の漏れ防止や資産の除却など、即実行できるものも多くあります。まずは現状を整理し、優先順位をつけましょう。
Q2. 無理な節税は税務調査で指摘されませんか?
A. はい、グレーな処理は避けるべきです。重要なのは「正しい経理処理」と「証拠の保存」です。税理士に確認しながら行いましょう。
まとめ:節税は「早めの準備」と「正しい判断」がカギ
決算前の節税は、**「今すぐできること」と「来期に向けた計画」**を整理することが大切です。
京都の中小企業でも、ちょっとした工夫で税負担を大きく減らすことができます。
税理士法人ビジョン・ナビでは、決算前の無料相談を実施中です。
今期の利益状況に合わせた最適な節税アドバイスを受けたい方は、お気軽にご相談ください。

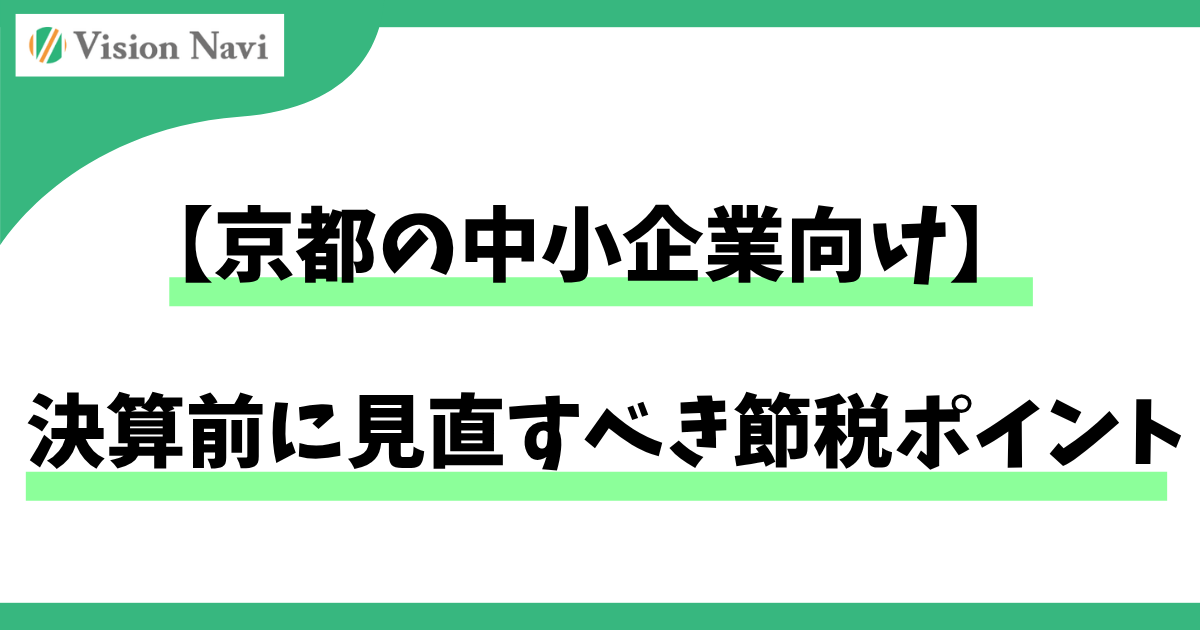

.png?width=750&name=%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%20(3).png)
.png?width=750&name=65%E4%B8%87%E5%86%86%20(1).png)